2021年の全米図書賞受賞作。本書の紹介の前に、ここ数年のアメリカの文学賞受賞作で差別を扱った作品について考えてみよう。つまり、オバマ大統領当選によって「人種差別は終わった(ポスト・レイシャル)」と言われた時代以降に「人種差別(レイシャル)」を扱った作品だ。私はそこに2つの潮流が存在すると考えている。
まず思い浮かぶのは、コルソン・ホワイトヘッドとジェスミン・ウォードであろう。いずれもすでに日本で紹介され人気も高いので説明は省くが、この2人はいずれも(設定は異なれど)人種差別をストレートに書いている。フォークナーの影響濃いウォードのように、ある種の伝統的な作風ともいえるだろう。ネイティヴ・アメリカンを書き続けたルイズ・アードリックの2021年のピューリッツァー賞受賞作 The Nightwatchman などもその流れに加えられるか(過去記事参照)。
もうひとつは、人種差別をアイロニーやコメディとして、変化球的に書いた作品たちだ。2015年の全米批評家協会賞・2016年イギリスのブッカー賞受賞作のポール・ビーティ『セルアウト(The Sellout)』、そして2020年の全米図書賞受賞作チャールズ・ユウ『インテリア・チャイナタウン(Interior Chinatown)』(いずれも過去記事参照)。この2作品は2022年2月現在いずれも未翻訳。すべて素晴らしい作品群だがその片方しかまだ日本に紹介されていないことは残念としか言いようがない。
そして2021年の全米図書賞を『ヘル・オブ・ア・ブック(Hell of a Book)』が受賞したことで、その2つの潮流が確立されたと言える。『ヘル・オブ・ア・ブック』は後者の潮流に属する作品であり、人種差別をコメディのメタフィクションに絡めているからだ。
とにかく本書は笑える。私は英語・日本語問わず、本を読んでここまで笑ったことはない。とにかくまずは本書35頁の書き出しだ。ちょっと訳してみよう。
申し訳ない。まだ俺の自己紹介をしていなかった。俺は著者、名前は────。俺の名前を聞いたことがあるかどうかはわからないが、俺の本のことは聞いたことがあるはずだ。かなり売れてるからね。その本のタイトルは『ヘル・オブ・ア・ブック(素晴らしい本)』。そしてレビューによれば、それは素晴らしい本なんだそうだ。 店舗販売されているし、オンラインでも買うことができる。Kindleやkoboにもあるし、iPadにもオーディヴルにもある。映画化できるようオプションもつけられていて──ジョセフ・ゴードン=レヴィットとドナルド・グローヴァーの2人が興味があると公言している。さらにはコミック化も検討しているところだ。
なんと語り手は、小説内で『ヘル・オブ・ア・ブック』という本を書いている著者なのだ。内容を簡単に要約すると、本書『ヘル・オブ・ア・ブック』は、作中内小説でベストセラーの『ヘル・オブ・ア・ブック』のブックツアーのお話だが、作中内小説『ヘル・オブ・ア・ブック』の内容は説明されず、分かることは誰もが作中内小説『ヘル・オブ・ア・ブック』を「ヘル・オブ・ア・ブック(素晴らしい本)」だと認めているということだけ。なんてこった。
作品内小説『ヘル・オブ・ア・ブック』の著者は名前を最後まで明かされることはないが、本書『ヘル・オブ・ア・ブック』の著者の名前はJason Matt(ジェイソン・モット)。ノース・カロライナ州のボルトン生まれ。ノース・カロライナ大学で芸術や詩を学び、2013年、The Returnedで作家デビュー。この作品は、Resurrectionというタイトルでドラマ化されシーズン2まで放送された。このドラマは『よみがえり〜レザレクション〜』として日本でも観ることができ、同名のタイトルでハーパーコリンズ・ジャパンから新井ひろみ訳で邦訳もされている。『ヘル・オブ・ア・ブック』は4作目の小説となる。
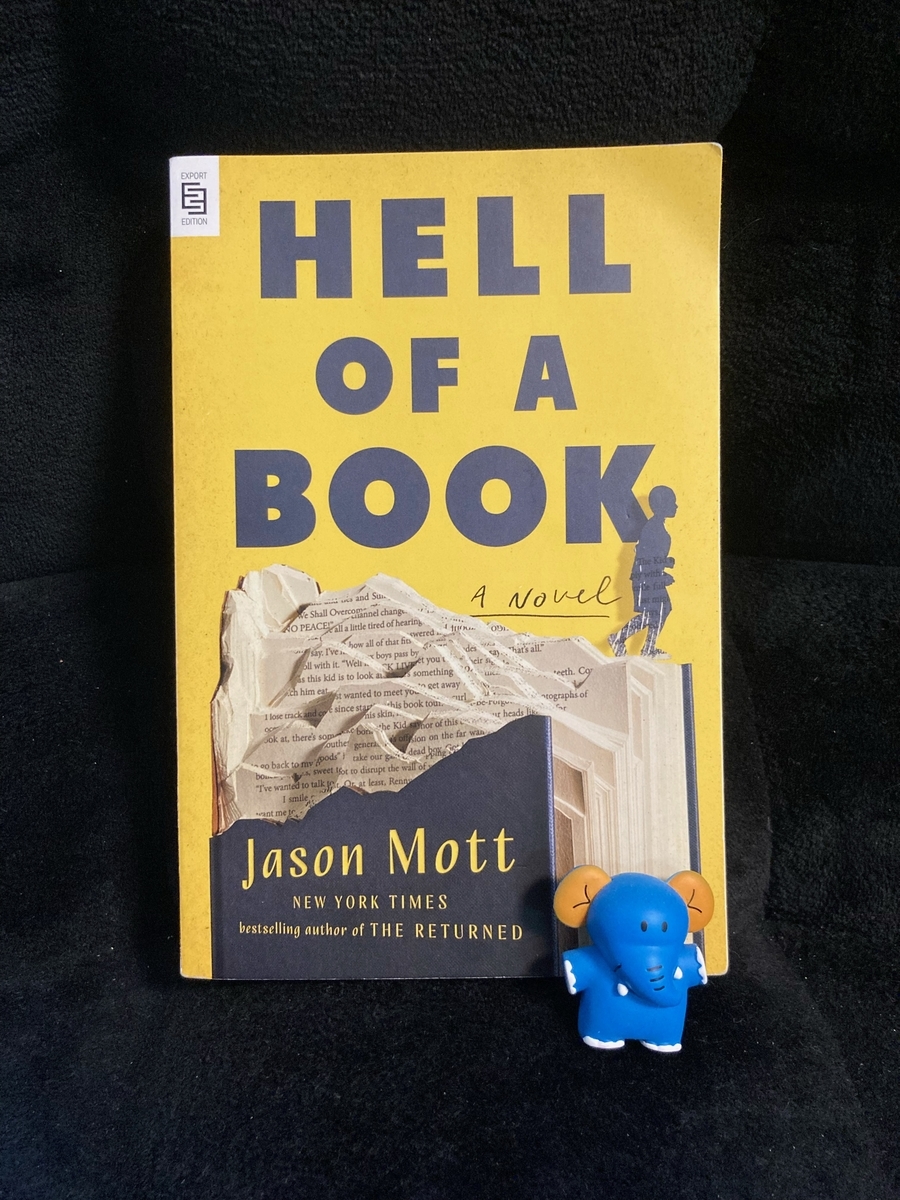
カロライナの青い空の下、荒れた道の突き当たりにある小さな田舎家、その小さなリビングルームの一角、黒い肌をした5歳の少年は両膝を胸まで引き寄せ、黒い両腕で脚を包んで座り、鼓動を打つ胸の籠の中へ笑い声を押さえつけるのに精一杯だった。(3頁)
少年はリビングルームで隠れているのだが、少年の両親はすぐ近くにいる息子がどこにいるのかわからない。この両親は息子が「見えないもの(The Unseen)」になれるようずっと願っており、父は魔法をかけるような仕草をしながらこう伝えていた「お前は生きてる間ずっと、透明で安全な存在になるんだ」と。そしてついに息子は両親の願いどおり「見えないもの」になることができた。 父は「見つからないから、別の子どもを探しに行こうか」と冗談を飛ばし、少年の母は「あの子の好きな料理を作って待っていよう」と提案、調理を始める。美味しそうな料理に胸をときめかせたまま少年は寝てしまう。少年が目を覚ますと、父に見つかり抱き抱えられていた。
父が少年を離すと、母は少年にキスをして尋ねた。 「どこにいたの?」 「できた!」少年は喜び叫んだ。「ほんとうにできたんだよ!」 「できたって、何が?」父が言った。 「透明になれたんだ!」
それを聞いて踊りながら喜ぶ3人。その翌朝、本当に見えていなかったのかと聞く少年に対して、父は「見えたか見えなかったはどうでもいいんだ」「本当に大事なのは、お前が安心していたかどうかなんだ」と答える。
覚えておいて欲しいこと:何よりもこの話はラヴ・ストーリーだということ。このことは絶対に忘れないで欲しい。 でもいまはそれよりも、まず俺のことを知ってもらおうか。今は午前3時だ。 午前3時。 午前3時、俺が今いるのは中西部のどこか──誰もが本来より素敵に見える、平原広がる州のひとつ。俺がいるのはホテル、そのホテルの廊下だ。そして俺は走っている。いや、正確には全力疾走。つまり俺は中西部のホテルの廊下を全力疾走している。俺が裸だってことは伝えたっけ? なぜならいま俺は裸だからだ。 追記:俺は追いかけられている。 俺の約15フィート後方には──俺のように全力疾走している、裸ではないが──非常に大きな体格をした男性が、非常に大きな木製のコートハンガーを握っている。バトンを握っているように見えるし、頭の上で振り回すと戦斧のようにも見える。あのサイズの男性にしては驚異的な足の速さだ。(中略)「妻だ! 俺の妻だったんだぞ! 子どもだっているんだぞ!」(10-11頁)
語り手である「著者」はどうやら不倫しているところを見つかり慌てて逃げている最中。そこに運よくエレベーターが到着、青い髪をした80代に見える高齢の女性が乗っていたが滑り込んだところで扉が閉まりなんとか難を逃れる。その女性ととりあえず会話を始める語り手。やがて女性はこう尋ねる。
「あの少年の話は聞きました?」 「どの少年ですか?」 「テレビでやっている子ですよ」彼女が頭を振ると、寄せては返す波を長いあいだ見過ぎてしまった人魚のように、青い髪が優しくなびいた。「恐ろしいこと、本当に恐ろしいことです」 「そうですよね、奥様」俺は言った。 本当のところ、突然彼女が悲しみを現したテレビの少年が何なのか聞いたことがなかったし、どれくらいの悲しみや配慮を伝えるのが適切なのかもわからなかったのだが。(15頁)
語り手はエレベーターを降り自分の部屋の前に立つが、荒れ狂う男性の妻の部屋にパンツごとルームキーを忘れていたことに気がつく。語り手は裸のままフロントまで行き、部屋に入れてもらうよう頼む。
「では、身分証などはお持ちでしょうか?」 俺はフロントから離れて雑誌の棚の近くまで行き、『ウィークリー・エンターテイメント』を一冊取り出した。俺の美しい顔が実物よりも大きく表紙に映っており、ニコラス・ケイジの最新作でいかにもニコラス・ケイジ的映画の見出しが隠れるほどだ。その上にデミヘルベチカ書体で大きく書かれた見出し:アメリカでいま一番熱い作家。その表紙を顔の隣に掲げて言った。「これでどう?」(17頁)
そのあとも様々なハプニングが起きて翌朝、「アメリカでいま一番熱い作家」である語り手はホテルで朝食を食べている。そこで語り手はとある少年(The Kid)に話しかけられる。その少年はありえないほど黒い肌をしていた。
「あなたとお話したかったんです」少年は言った。 俺は最上級の「ファンに会うのはいつも最高だぜ」という笑顔をして言った。「君の本にサインしてほしいのかな?」 少年はにっこりした。「ううん」そして言った。「ファンじゃないんだ。ただあなたに会いにきただけ」 「かまわないよ」俺は言った。このブックツアーを始めてからというもの、この手のファンにも少しだが会ったことがある。臨機応変ってものを学びつつあるようだ。「うん、君に会えてぼくも嬉しいよ」(24頁)
少年の黒さと雰囲気にどこか恐怖を感じながらも簡単な会話を続ける2人。少年は最後に「あなたにぼくのことを見てほしかったの。それだけなんだ」と伝える。
俺は少年へ最後の笑顔を返した。彼の穏やかで豊かな言葉遣いに敬意を表して。「あなたに私のことを見てほしかった」人にそう伝えるのは実に美しいことだ。つまり、俺たちはみんな誰かに見ていてもらいたいものなんじゃないだろうか? 俺は席を立つ前に少年の近くまで屈み、心を込めてこう言った。「ぼくには君のことが見えるよ」 それから自分の部屋へと戻った。(25頁)
少年の章へと戻る。10歳になった少年だったが、1章での出来事以降、透明になれることはなかった。そのあまりにも黒い肌から少年は「Soot(煤)」というあだ名で呼ばれ、スクールバスで揶揄われる様子が描かれる。 再び「著者」の章となり、冒頭に引用した場面になる。「著者」は自己紹介を済ませたあと、かつて作家になる前にコールセンターで働いていた昔話を始める。爆笑のエピソードが次々と語られるが、最後は友人と「あの少年に起こった悲劇」の話になり、「著者」はなんのことかわからないまま適当に話を合わせるのだった。 何層にも重なる「ヘル・オブ・ア・ブック」 「著者」は、ブックツアーで訪れる街で同じことを何度も聞かれる。それは『ヘル・オブ・ア・ブック』の内容についてと、エレベーターでの老婆と昔話での友人から話を振られた「少年のニュース」について。この小説が「ヘル・オブ・ア・ブック(素晴らしい本)」である理由は、その2つの質問が一向に説明されないことだ。 「著者」が書いた『ヘル・オブ・ア・ブック』には何が書かれているのか、「少年のニュース」とは何なのか、そして「著者」の前に何度も現れる少年(The Kid)とは何者なのか。そのプロットに「煤」と呼ばれる少年がどう絡んでいくのか……。この強烈な引きによって読者は頁をめくり続けていく。
「それでどう思うんだ?」 「それでって何が?」 「あれについてどう思ってるんだ? あんたは作家だろ。あれについて何か言うべきだと思われてるんだよ。あんた黒人だし!」 「え、俺?」俺は自分の腕を見た。ああ、ほんとだ、レニーの言ってるとおりだ。俺、黒人じゃん! 今更ながら驚くべき発見だ! 「ええっと、まあ」俺は言った。黒い腕の先にある黒い手と、その先についた装飾のような黒い指を見つめながら。「これは本当に、本当に面白いな。俺の読者はこのこと知ってたのかな?」(76頁)
「『著者』の人種を勝手に設定してなかったか?」と読者に問いかけるシーン。「著者」は自分でも『ヘル・オブ・ア・ブック』に何を書いたか把握しておらず、自分の過去さえ不正確なことが判明していくが、そうすることで「著者」は読者の容れ物と化し、「おまえはあの少年のニュースについてどう思うんだ?」の問いは直接的に読者への問いになる。 こうして、読者は本書を読み進めていくことで作中内小説『ヘル・オブ・ア・ブック』だけでなく本書『ヘル・オブ・ア・ブック』の内容を補完していくような、自分も一緒に『ヘル・オブ・ア・ブック』を書いているような感覚に陥る。なんてこった。 以降、若干のネタバレを含みつつもう少し本書を説明していこう。邦訳を待ちたい人などは注意。 「少年」の正体が作品全体に及ぼす影響 ストーリーとして中心になるのは、作中内小説『ヘル・オブ・ア・ブック』の内容と「少年(The Kid)」の正体だ。中盤あたりで何度も突然現れる「少年」を、「著者」は「幻」だと思うようになる。「少年=幻」がこの小説にもたらす効果は2つある。 人種差別をコメディの枠組みで書いた先行作『セルアウト』『インテリア・チャイナタウン』と異なる点は、『ヘル・オブ・ア・ブック』には伝統的なモチーフがいくつか登場するところだ。「煤」の語りでの「見えないもの(The Unseen)」がラルフ・エリスン『見えない人間(Invisible Man)』を連想させるのもそのひとつだが(「煤」の語りも非常によく書けており、読者は強烈な怒りと悲しみを抱くだろう)、本書で最も重要なのはトニ・モリスン『ビラヴド』からウォード『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』へと連なる子どもの幽霊、つまり「少年=幻」だ。『ヘル・オブ・ア・ブック』に登場する「少年」はある特定の少年のことであるが、それと同時にこれまでの悲劇とこれからも繰り返されるであろう悲劇の象徴にもなっている。「著者」が時と場所に関係なく「あの悲惨なニュースを聞いたか」を耳にする理由も納得するであろう。こうして「少年=幻」の設定は黒人差別小説としての『ヘル・オブ・ア・ブック』をその伝統と結び付ける。 そして「少年=幻」によるもうひとつの効果。「著者」は、他の人物には「少年」が見えていないことで、いま自分が目にしているのは現実なのか非現実なのか(real or unreal)が揺らいでくる。これこそメタフィクションが最も得意とするテーマであり、この要素が加わることでメタフィクション小説としての『ヘル・オブ・ア・ブック』の強度が高まる。 後半に差し掛かる頃、航空機のファーストクラス内で「著者」はとあるハリウッド俳優から『ヘル・オブ・ア・ブック』にサインを求められる。ここでハリウッド俳優は「著者」に様々な言葉を伝える。
「あなたが何かを見たとき、そいつはあなたの脳内でストーリーを作り上げる。やがてそのストーリーはあまりに説得力に溢れているので、結果的に現実を飲み込んでしまうのだ」(194頁)
この「見る(see)」という言葉がラストに向けて重要なキーワードになっていく。この小説の始まりを思い出して欲しい。「煤」の両親による「見えないもの(The Unseen)」になるという願い、「著者」の前に現れた「少年」の「あなたにぼくのことを見てほしかったの」という言葉……「見る」というキーワードは、現実か非現実というメタフィクション的な問いに差別とどう向き合うのかという問いを加える。もちろんその問いも匿名の「著者」を通して読者の眼前に現れる。「あなたには何が見えているのか?」と。 冒頭の会話が重要なキーワードとして伏線になっていたように、一見関係ないような記述が後半になって回収されたりしていて、その辺りも非常に良く練られている。この記事を書くためにパラパラ読み直したら様々な気づきがあり、もしかしたら2回目の方が面白いんじゃないかという気もしてくる。冒頭の「何よりもこの話はラヴ・ストーリーだということ。このことは絶対に忘れないで欲しい」という宣言、ホテルで裸の著者が突然エレベーターに入ってきたのにどうして老婆は平然としていたのか? 190頁で唐突に出てきたハリウッド俳優は序盤ですでに……ここら辺で止めておこう。 黒人差別の悲劇と爆笑のメタフィクションとを完璧に両立させた『ヘル・オブ・ア・ブック』、文句なしにヘル・オブ・ア・ブック(素晴らしい本)です!!